
【連載】日本の歯科と北欧の歯科の違いとは?~アンチエイジング治療の動向とトレンド~
2018.11.30
歯科をめぐる国民性の違いとしてよく引き合いに出される地域が「北欧」です。その先進性、予防意識の高さははたしてどういった違いによって引き起こされたものなのか。本連載では服部先生に現状と今後の予想を伺ってきました。
北欧の歯科事情は、制度事情の違い
社会保障の手厚さでよく比較される北欧では、多くの国が歯科領域にもさまざまな制度設計をおこなっています。スウェーデンはかつて日本よりも遥かに小児虫歯の多い国でした。しかし30年ほど前に虫歯根絶に取り組んでから、子どもの虫歯は日本の約10分の1以下に。国民は3歳から予防歯科のプログラムを学び始め、学校・職場、さまざまな啓蒙活動に触れることができます。
ある統計では4人に1人は一度も虫歯になることがありません。80歳の平均残存歯数は25本を超え、予防歯科受診率は90%を超えています。
これは、「19歳以下の国民は歯科診療代は無料」という制度によるものです。幼い頃から予防医療に親しみ、歯を健康に保った状態で20歳を迎えるのです。20歳以上でも歯科治療には補助金が支払われ、常に定期検診を受けることが奨励されています。
治療方針の違いも制度設計によるもの
また、これらの制度の違いは治療方針の違いにも繋がります。「削る治療」「削らない治療」はもちろん、スウェーデンではさまざまな治療が幅広く歯科治療として認められており社会保障の対象となります。しかし日本では保険適応/保険適応外の境目に特徴があるのは皆さんご承知のとおりです。技工士・衛生士のレベルは概して高く、それぞれの人にそったオーダーメイドの治療を手がけることができるように訓練を受けています。
日本の歯科医師はどうしても「師事した方の方針」に強く影響を受けざるを得ず、横断的に新しい知見を得るのに乏しい現状です。
歯科医師は自己投資してレベルアップしていかなければならない
自費研カタログ関連商品
自費研カタログ関連商品はありません
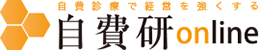
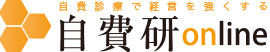


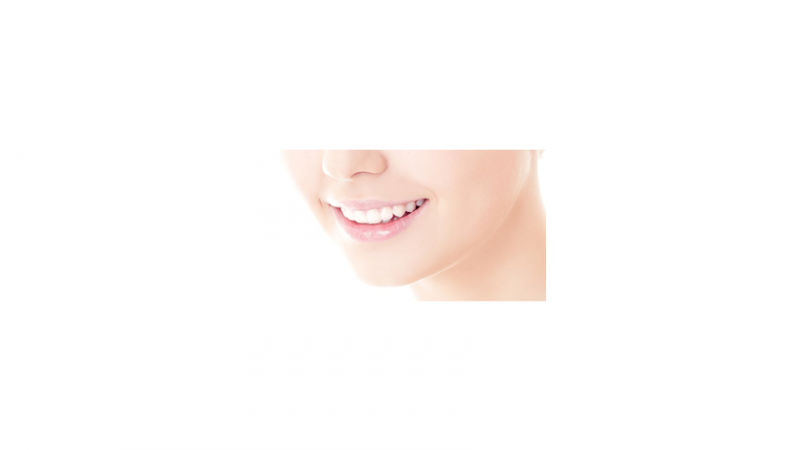

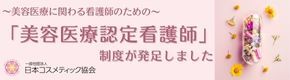



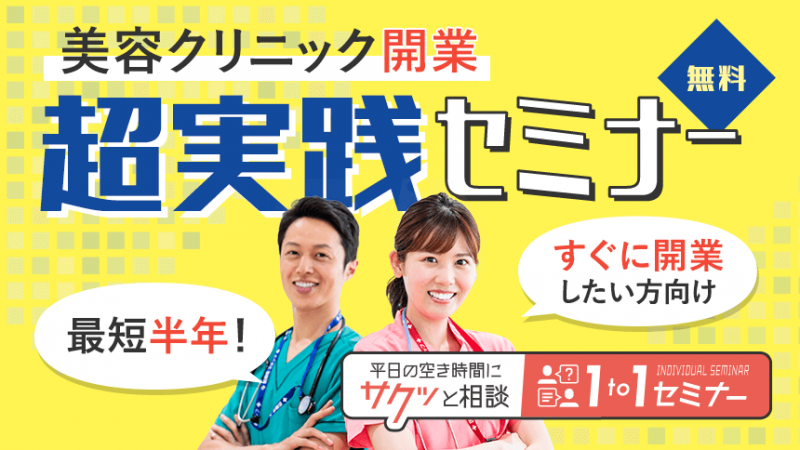










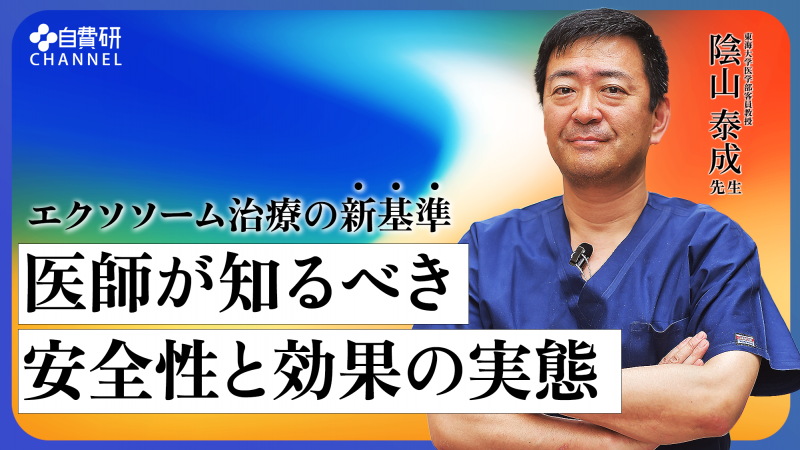
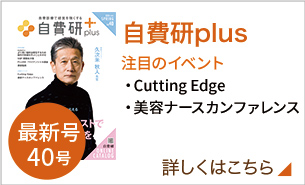
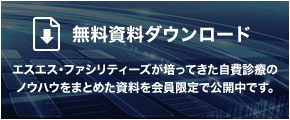


Clipを上書きしてもよろしいですか?