
国内で先駆的な腸内フローラ移植に取り組んでいる医療機関 (第三回)
2018.05.10
院長自身が潰瘍性大腸炎の罹患経験を持ち、自ら腸内フローラ移植の効果を実感している立場から院長ご自身のクリニックで実施しているフローラ移植および関連治療の現状を語っていただきました。三回連載のコーナーとなり、今回は第三回となります。
患者さんが主体的に治していく意識を持って取り組むモチベーション維持のために医療機関が果たしていくべき具体的な役割とは
今後、『食』がキーポイントになると予見しています。たとえ腸内フローラ移植をしたとしても移植後は不摂生して良いという認識を持って欲しくはありません。
現代の日本の食事には、圧倒的に精製された糖質が多く、腹部症状や精神症状など様々な症状の改善に対して足を引っ張ってしまうことが少なからずあります。摂取する糖質の選択をきちんと行うことが必要で糖質制限とは区別して考えていく必要があり、正確な情報を把握して賢く食材を選んでいただくことが患者さんには必要なことだと思います。
患者さんには腸内フローラ移植後の良い状態を維持するように自己管理をしてもらう前提で食事指導を実施しています。当院では管理栄養士がヒアリング項目を作成するとともに個別に聞き取りも実施しており、移植時にそれまでの食事の実態を把握した上で、移植後の提案として、実践可能な具体的な内容を患者さんに伝えています。
当院では根本治療を目指しているため、患者さんが主体的に治していくという意識をもって取り組んでいただくためにモチベーションの維持が最も大切になってきます。根本治療に腸内フローラ移植が最も近いとは考えているのですが、移植後は放置せずに自分の健康に責任を持っていけるのかというようなところをきちんと教育して、主体性を持っていただくことも必要となります。効果的な移植後のサポートを行うためにも心理カウンセラー(臨床心理士)による心理テストを実施し、効果・変化の程度も確認していきます。
元々は院長自身が、がんの心理療法なども診療していた経験から根本治療とは前述のようなことで栄養治療だけではなく、全人的に診るというスタイルが診療方針の基盤になっています。
全人的な医療を実践する上で保険診療だけを実施して患者さんのニーズに応えていくのは難しいのが現状です。自費診療を考慮に入れていくことは、患者さんの選択肢が増えるという意味で双方にとって良いことではないかと思えます。
サプリメントも良いのですが、食品を処方箋の一環として出せるようにしていきたいと思っています。
自費研カタログ関連商品
自費研カタログ関連商品はありません
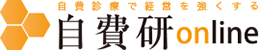
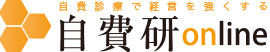


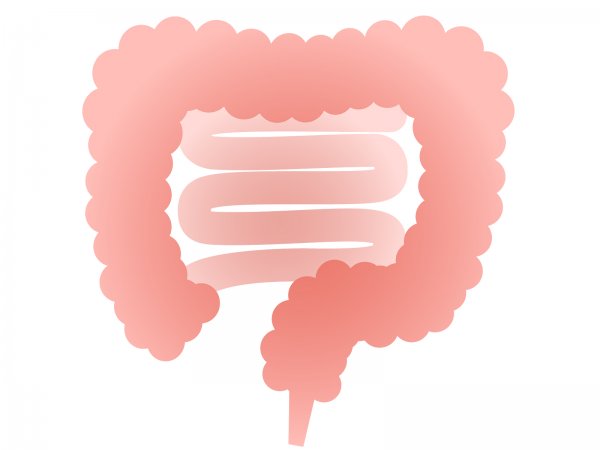



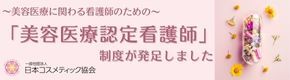



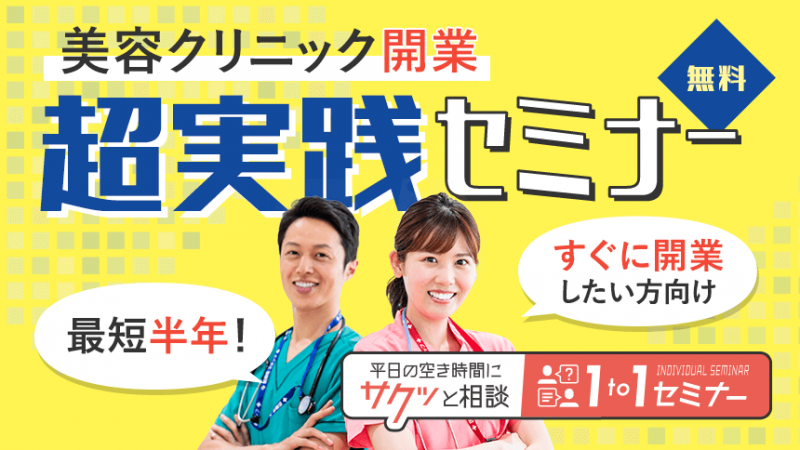










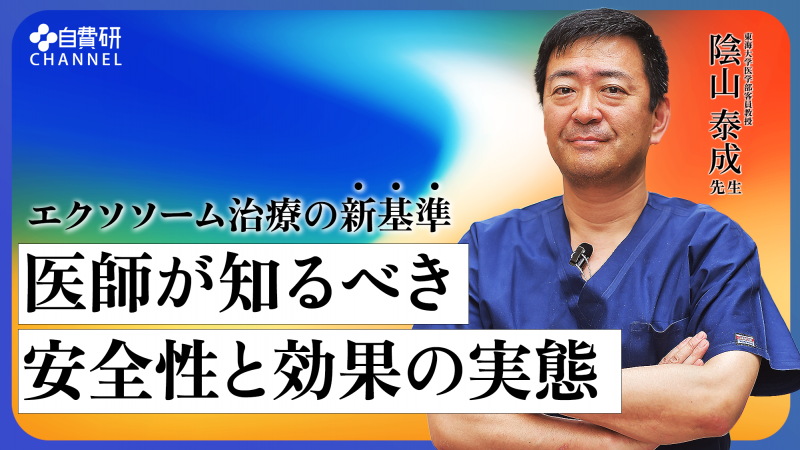
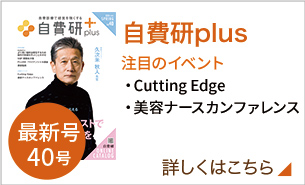
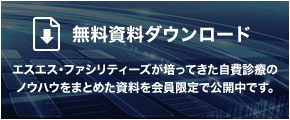


Clipを上書きしてもよろしいですか?