
【第二回】 腸が重要な臓器となる理由(わけ) 人類は腸管から進化してきた
2018.05.17
腸内細菌・腸内環境の研究に着手したきっかけを起点に、常に生き物の原点を見据え、豊富なご経験を踏まえた目線で「これからの医師に求められる必要な視点」に到るまでの話を本領域の第一人者である藤田先生に語っていただいた。
誰にでも効く乳酸菌は存在しない
腸内の善玉菌と日和見菌を増やすことが重要
近年では、がん治療で遺伝子診断が行われるのが当たり前となってきたように、腸内細菌も人によって体内での内容構成が異なります。人の腸内細菌の種類は、生まれて1歳半になるまでに決まります。産道を通り、母乳を与えられ、離乳食、触れあう人などによっていろいろな種類の腸内細菌が定着します。腟にはデーデルライン桿菌が定着しており、母乳には700種以上の細菌が含まれています。
つまり、どのような環境で育てられたかによってその人の腸内細菌も違ってきます。私は大連生まれで、私を育ててくれた乳母は韓国の女性、母は京都生まれですから私の腸内細菌はキムチや漬物由来の腸内細菌なのでしょう。
前述したように次世代シーケンサーの登場で、近年では一人ひとりの腸内の細菌が違うことがわかってきています。重要なのは腸内の善玉菌と日和見菌を増やすことです。乳酸菌は必ずしも生きた状態で腸内に届く必要はなく、乳酸菌の死骸はその人の腸内に定着している乳酸菌を増やす因子となります。しかし、どのタイプの乳酸菌がその人の乳酸菌を増やす因子となるかはわかっていません。
誰にでも効く乳酸菌は存在しないのです。その人に応じたかたちで定着している腸内細菌は違うため、ある人にとっては腸内の善玉菌を増やす乳酸菌が、別の人の善玉菌を増やしてくれるとは限りません。
したがって特定の乳酸菌や薬を1種類のみ摂取するのでなく、何種類もの乳酸菌や発酵食品、食物繊維を摂り、善玉菌の増殖因子および腸内細菌の種類を増やし、腸内フローラのバランスを整えることに着目すべきと考えます。
自費研カタログ関連商品
自費研カタログ関連商品はありません
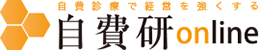
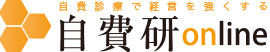


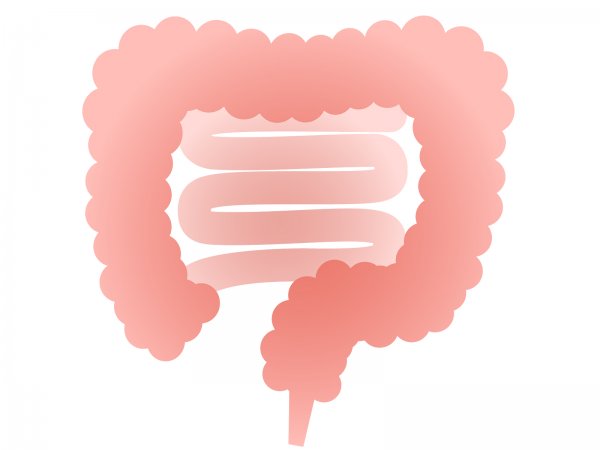


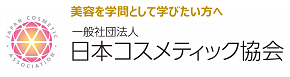




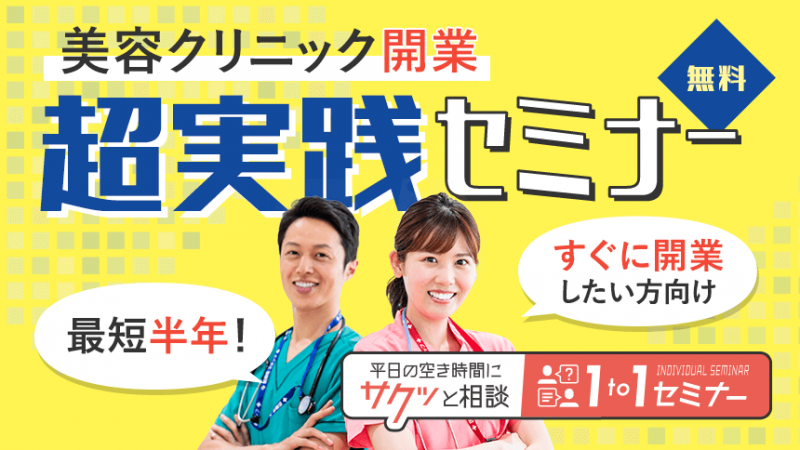






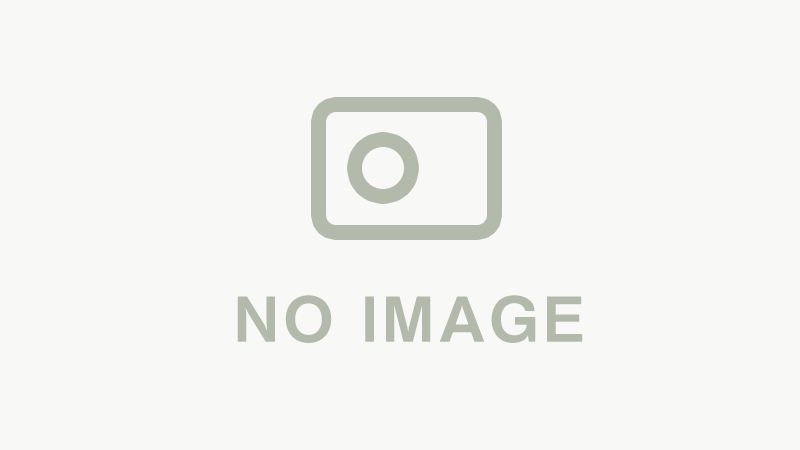



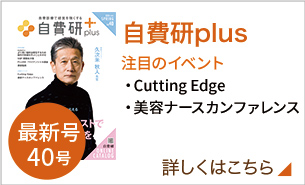
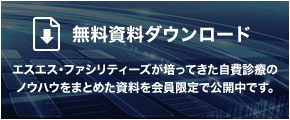


Clipを上書きしてもよろしいですか?