4

医療の現場で求められる「やさしい日本語」とは
2020.04.22
「やさしい日本語」をご存知ですか?17日に東京が開設した外国人向け相談窓口「東京都外国人新型コロナ生活相談センター(Tokyo Coronavirus Support Center for Foreign Residents=TOCOS=トコス)」でも、一次対応に「やさしい日本語」を使用することが発表されていました。日本で暮らしながら日本語を母語としない人たちの、不安解消のための取り組みが各所で進められています。有事に限らず、クリニックに訪れる外国人患者への伝え方を、この機会に改めて考えてみましょう。
震災をきっかけに生まれた「やさしい日本語」
「やさしい日本語」は、日本語に不慣れな外国人にも伝わりやすいように配慮した日本語のことをいいます。
「やさしい日本語」が生まれたきっかけは、1995年の阪神淡路大震災。外国人被災者のための情報提供までに、発災から半日の時間を要したことや、英語を理解できないことで困難な状況におかれた外国人が多くいたことから、迅速に簡潔で正確に伝えることを目的に、弘前大学・社会言語学研究室により考え出されたのがはじまりでした。
現在では災害時だけでなく、平時の情報提供ツールとして、観光や報道のツールとしても使われ、共通言語的な役割を担っています。オリンピックにむけ、今またその重要性が注目されています。
「やさしい日本語」作り方のポイントは
外国人にわかりやすい「やさしい日本語」を作るために…
・主語と述語を明確に、一文を短くする
・難しい言葉を簡単な語彙に言い換える
・擬態語や擬音語を使わない
・カタカナ外来語を使わない
細かなポイントは沢山ありますが、大切なのは、簡単な表現を使うこと、文章の構造を複雑にしないことです。万が一「やさしい日本語」でうまく伝えきれず、機械翻訳を使う時にも、一度文章を簡単にすることで、意味の伝わりやすい訳文が表示されます。仮に通訳者がいたとしても、通訳者の医療知識にも差があります。やはり「やさしい日本語」にすることが大切です。
自費研カタログ関連商品
自費研カタログ関連商品はありません
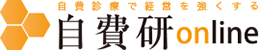
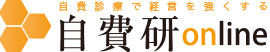






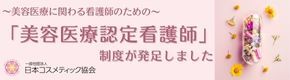



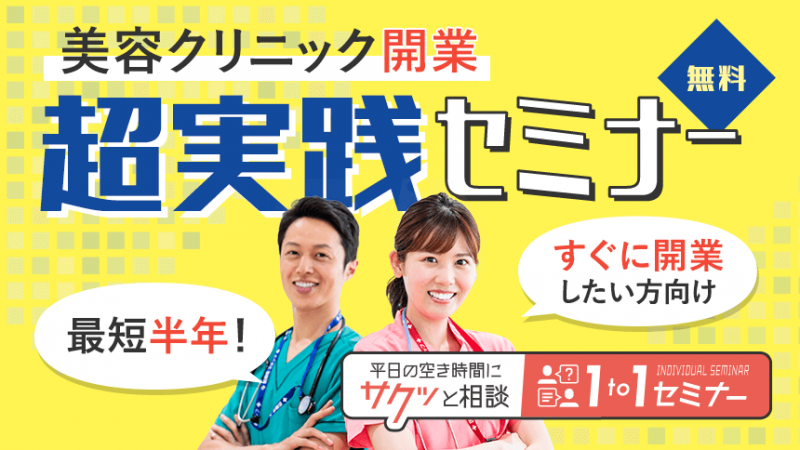










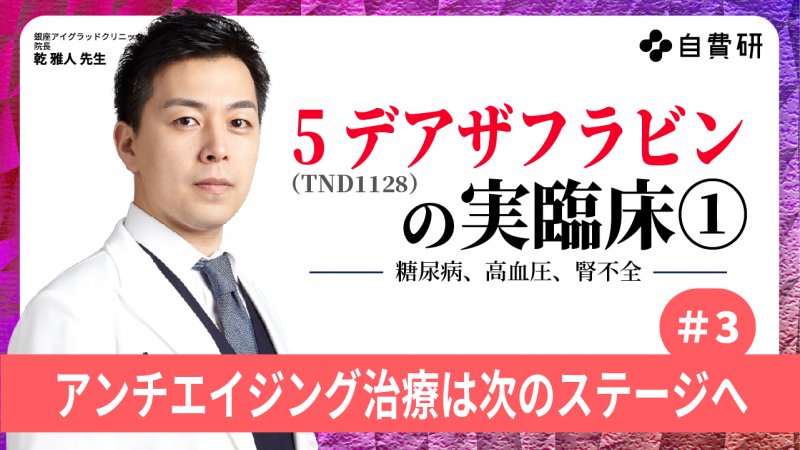
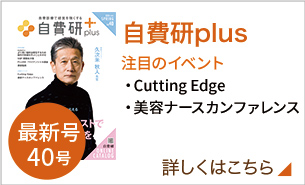
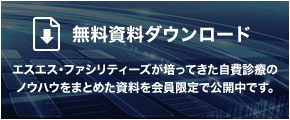


Clipを上書きしてもよろしいですか?