1
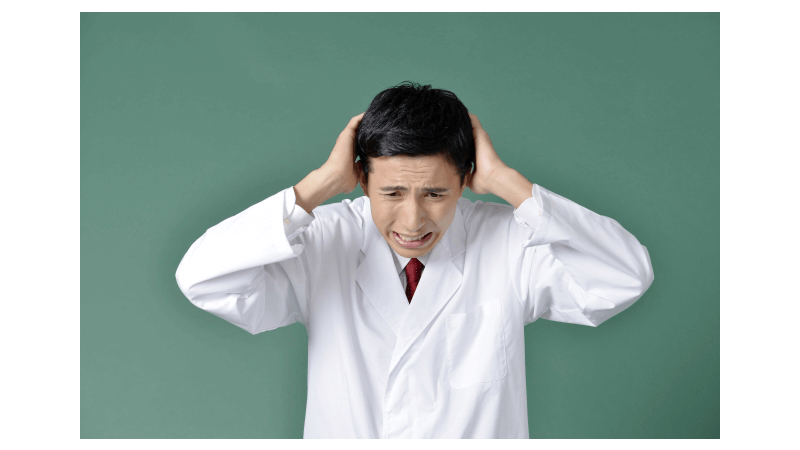
医師だけが知らない 患者さんのクレーム vol.1
2018.05.25
医療に関することで、どこに相談したらよいかわからず困った時などの保健所の窓口、「患者さんの声」。職員が話を聞き、必要に応じて関係相談先を案内する仕組みである。この「患者さんの声」相談員を務めた医療ジャーナリストが、医療機関へのクレームの実態を明かす。連載第1回。
クリニック検索サイトやクリニックHPに、患者さんからクレームを書き込まれ、落胆されたことはありませんか。ネットの書き込みは氷山の一角、院長の知らないところで、思いもよらない評判が立つことがあります。
筆者は取材業務の傍ら、約2年にわたり都内各所で「患者さんの声」相談員を担当してきました。「患者さんが藁をもすがる先端治療、名医」の情報提供をするに飽きたらず、患者さんは現行の医療サービスに満足しているのか。文字通り「患者さんの肉声」を拾ってみたくなったのです。
ここで、各地方自治体に設けられた「患者さんの声」相談についてざっと説明します。1999年に起きた横浜市立大学病院の「患者さん取り違え事件」を契機に設置された医療安全啓の行政サービスで、住民からの「医療にまつわる悩み全般」に応じる相談窓口です。
都内だけで相談件数は年間12000件超。「どこの診療科に行けばよいか」「近くの小児科を教えてほしい」といった基本的な相談が6割を占めます。では、残り4割は何か?
医療機関への苦情です。
都内だけで年間5000件超の医療機関への苦情が相談窓口に寄せられます。
苦情を訴える患者さんはなかなかの「知能犯」です。「開業医は所在地の自治体に開業届を出しているはずだ。役所には開業届を受理した責任がある。開業届を取り消せ」「あそこのクリニックは詐欺だ。保険診療の資格を取り消せ」「こういう苦情は地元医師会に投書をすればよいのか」など、ある程度の医療制度の知識を持ち合わせ、踏み込んだ発言をしてきます。
クリニックに乗り込んで「医療過誤だ、訴えてやる」と騒ぐ感情的なクレーマーは、院長や経営者も把握しやすく顧問弁護士に一任すれば済みます。ところがネットに書き込んだり、町内会や老人会、学校父母会などの地域コミユニティで拡散したり、消費生活センターや区役所、保健所、地元医師会に訴え出たりするのは、院長や職員が預かりしらぬトラブルで、発信源は匿名かつ不特定多数の知能犯。しかも人から人に語り継がれる伝言ゲーム。知らないうちにクリニックに影を落としていくのです。
「患者さんの相談窓口」は相談を聞くだけで、仲裁や介入はしません。役所のお仕事の定石です。患者さんは「では何のための相談窓口なのだ」と立腹されます。
当然です。怒りが収まるまで傾聴するしかありません。
先日、全国ニュースになった幼児虐待死は、家族が都内各所の相談窓口を転々としていた事例でもありました。
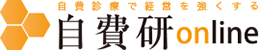
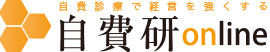



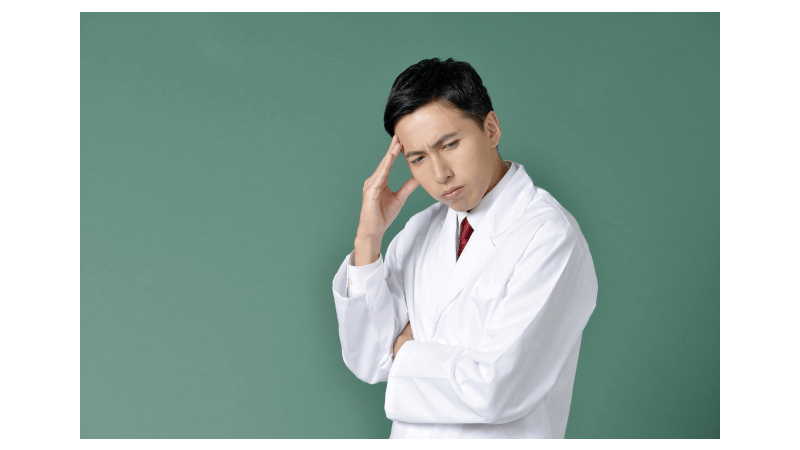

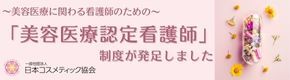



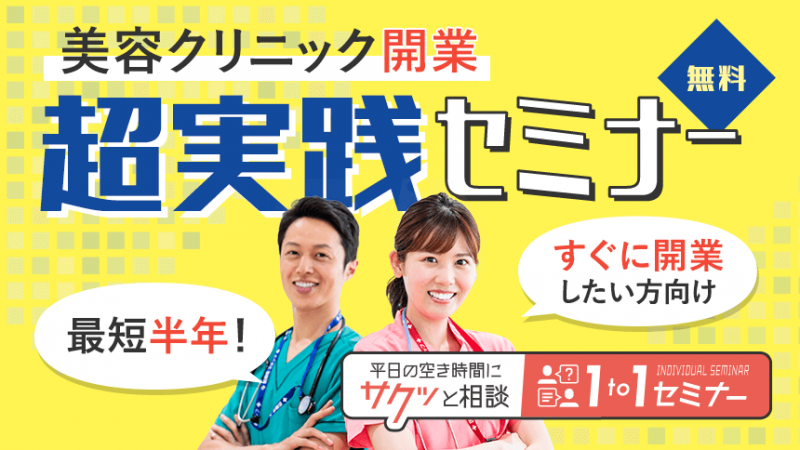










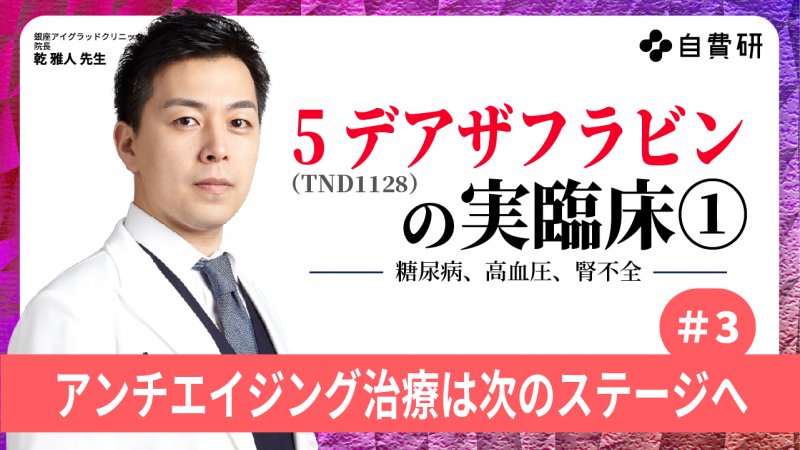
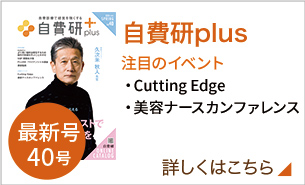
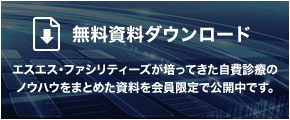


Clipを上書きしてもよろしいですか?