1
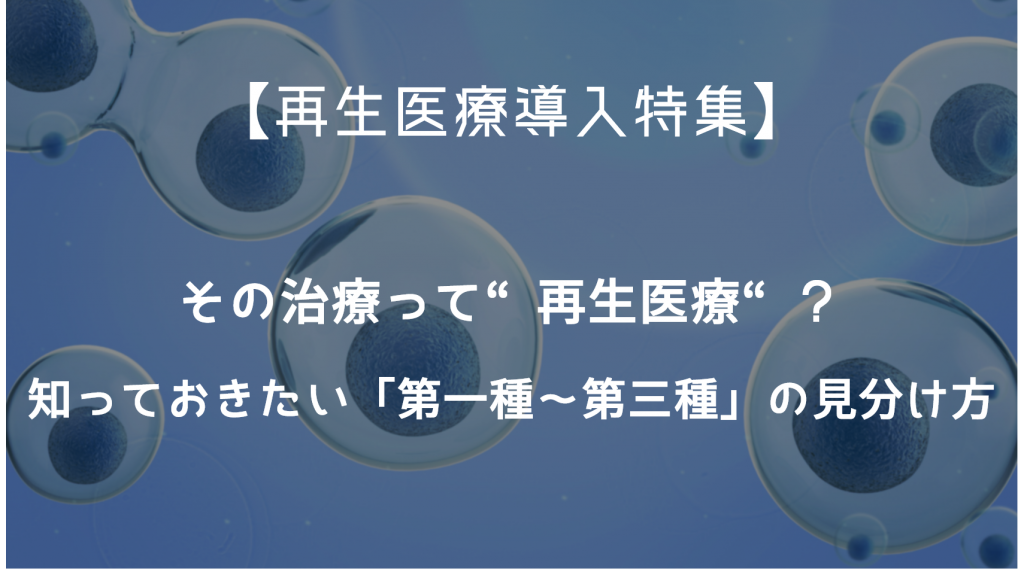
【再生医療導入特集】その治療って“再生医療“?知っておきたい「第一種~第三種」の見分け方
2020.10.22
近年ますます注目度の高まる再生医療。
巷には“再生医療”を謳った医療機器や医薬品、さらには化粧品まで、数多くの製品が出回っています。
曖昧な知識で治療を導入することは危険ですが、反対に「うちにはまだ早い」と倦厭していると、業界のトレンドにおいて行かれてしまいます。
「再生医療新法って?」「第一種から第三種まであるらしいけど、PRPはどこに当てはまるの?」「幹細胞培養上清液は再生医療…?」
自費診療を扱うクリニックなら絶対に知っておきたい基礎知識を徹底解説いたします!
『再生医療等の安全性の確保等に関する法律』はなぜ制定されるに至ったのか
再生医療を理解する上で重要となる法律『再生医療等の安全性の確保等に関する法律(以下:再生医療新法)』。再生医療の定義やクリニックでの治療の提供規則などは、全てこの法律によって取り決められています。まずは、この法律が制定されるに至った背景を見てみましょう。
再生医療の歴史は古く、かつては細胞療法として研究が進められていました。1970年代に表皮細胞、軟骨細胞等の分化細胞の培養技術が確立されると治療は飛躍的に進歩します。1987年には米国で自家培養表皮がFDAの承認を受け、1998年には米・ウィスコンシン大学のジェームズ・トムソンがヒトES細胞の樹立を発表。
そして2007年には日本でも、株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングの自家培養表皮が、国内初の再生医療製品として製造承認を受けました。同年、京都大学の山中伸弥教授がiPS細胞を発表したのも、世界の再生医療を大きく前進させる出来事として記憶に新しいのではないでしょうか。
しかしその背後では、クリニックで行われている再生医療や免疫療法を巡って、患者トラブルや死亡事例が発生しており、規制がない状態を問題視する声が上がっていたのです。
iPS細胞をはじめとした臨床研究の分野では、当時から厚労省がガイドラインを制定しており、そのルールに則った運用が求められていました。とはいえ、あくまでもガイドラインでしかなく法的根拠がなかったことから、山中教授をはじめ日本再生医療学会も法律による規制を強く要請していたのです。
そういった流れを受けて、厚労省は、国民が迅速かつ安全に治療を受けることが出来るようにと『再生医療新法』を制定。それまではクリニックでPRP療法を行うにも、国への申請は必要なく、設備さえ揃えれば患者に治療を提供することが可能でした。しかし2014年11月25日、厚労省により法案が施行されると、患者への提供にも明確なルールができ、事前申請や事後報告の義務などが発生するようになったのです。
再生医療の定義とは? ポイントは「細胞を使うかどうか」
自費研カタログ関連商品
自費研カタログ関連商品はありません
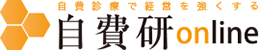
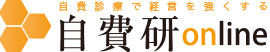

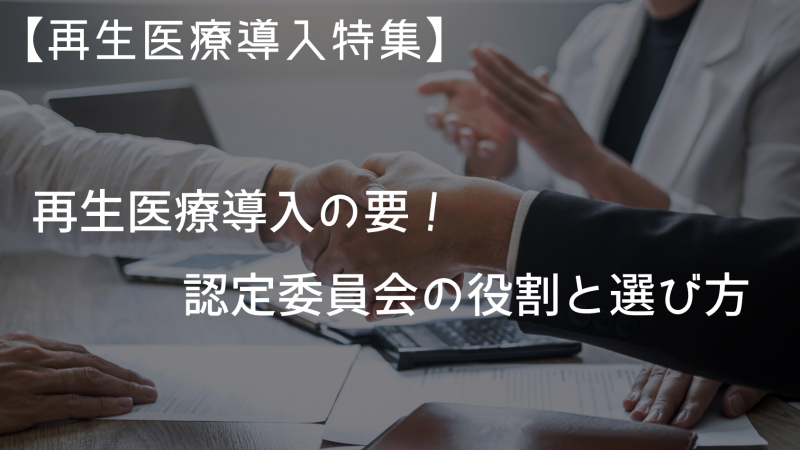
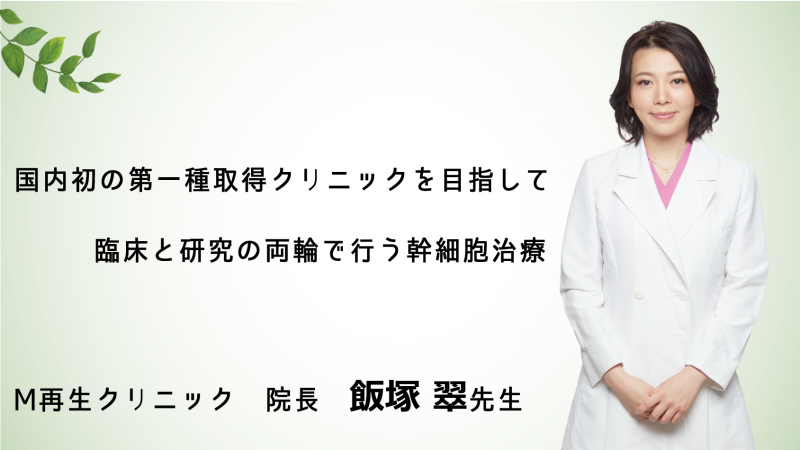
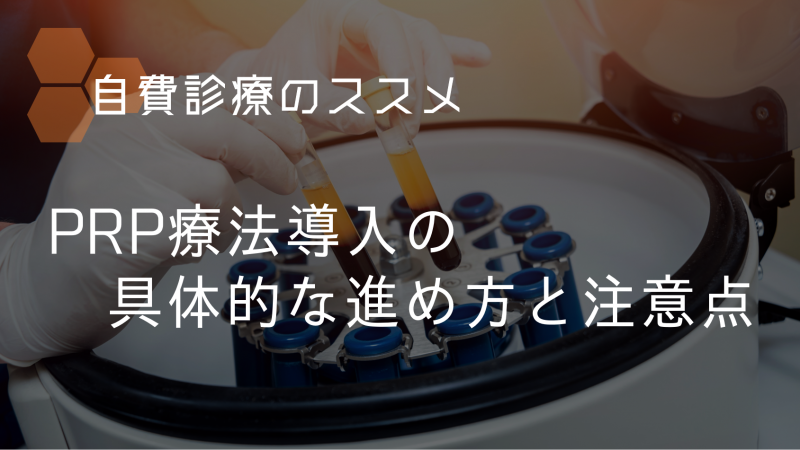
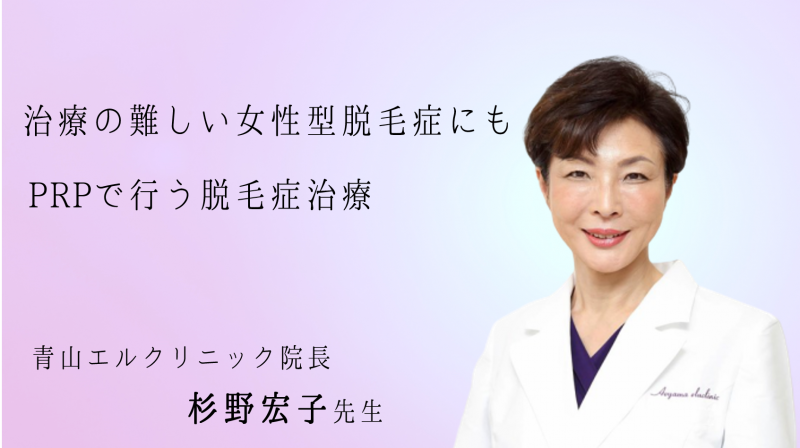

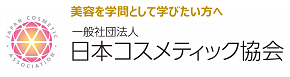




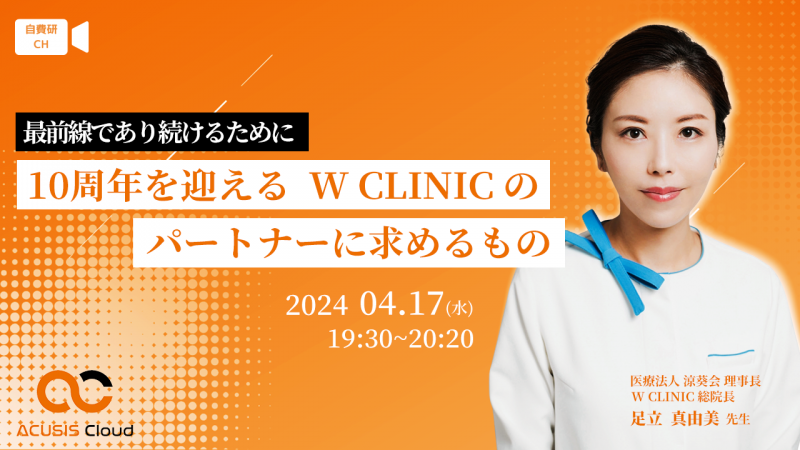
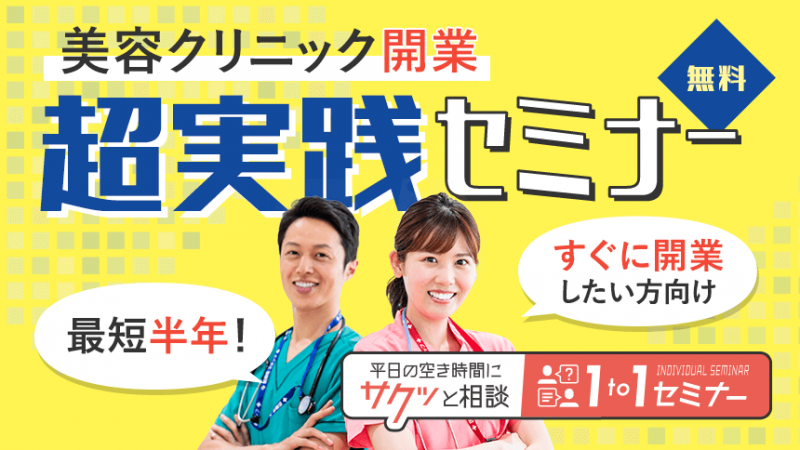





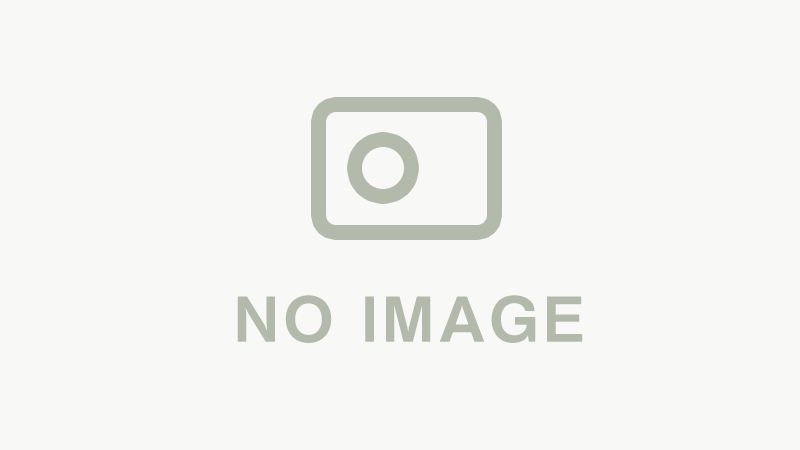



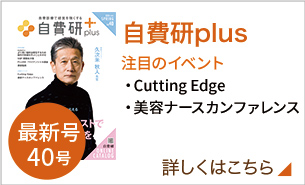
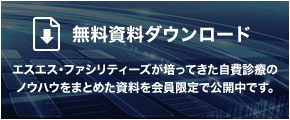


Clipを上書きしてもよろしいですか?